えっ?日本酒も?! 【九州には焼酎・日本酒の蔵元が多い】その理由とは?

九州のお酒といえば何といっても焼酎。鹿児島を中心に、たくさんの蔵元があることで知られています。でも、意外に日本酒の蔵元も多いのをご存じでしょうか? なぜ九州に蔵元が多いのか? データを元にその理由をひも解いてみました。美味しいお酒にはワケがあるのです!
酒造天国・九州

酒蔵の杉玉
平成27年度国税庁のデータ「都道府県別の製造免許場数」によると、「しょうちゅう」全体の免許場数は全国で968。そのうち鹿児島県が123と、やはりダントツで1位です。また、南九州(熊本・大分・宮崎・鹿児島)の合計は254と、全国の26%強。北部九州(福岡・佐賀・長崎)を合計すると341になり、なんと35%以上を九州の免許場が占めていることがわかります。
一方、「清酒」のデータで目をひくのは福岡県。74の製造免許場があり、これは新潟・兵庫・長野・福島に次いで全国で5番目に多い数です。大分県35、佐賀県も30と健闘。特に佐賀県は、「しょうちゅう」は10なので「清酒」の方が3倍。これらはちょっと意外な数字ではないでしょうか。
豊かな水のある米どころ・・・まさに日本酒造りにピッタリ!

豊かな田園風景
日本酒造りは、米麹の温度と湿度の管理が難しく、以前は管理しやすい寒冷地の方が主流でした。しかし技術の発達によりその問題も解消。特に、美味しい日本酒を造るために欠かせない“良い米と水”が揃う北部九州は、日本酒造りに適した場所としてますます発展しています。
データでも、日本全体の「清酒」免許場数は、例えば平成25年度の1879から平成27年度は1844と、近年減少が止まりません。しかし、そのなかでも北部九州は、120から121へと、逆に増加しているのです。
原料さまざま・・・多種多様な九州の焼酎

さつまいも「黄金千貫」
九州南部は、その地域の特産物を生かした焼酎造りが発達。特に鹿児島の芋、大分の麦は有名です。その他の九州でも、熊本は米焼酎、長崎は米麹を使った麦焼酎、福岡では珍しい胡麻や緑茶焼酎など、各地で特色ある焼酎が造られています。
おもしろいのは宮崎県で、隣県に近い地域それぞれで多様な焼酎が作られています。まるで焼酎パラダイス九州の縮図のよう。
豊かな自然に恵まれた九州だからこそ、美味しい日本酒や焼酎ができるワケですね! ぜひジャンルにとらわれずにいろいろ試してみて、新しい自分好みの一杯を見つけてみませんか?








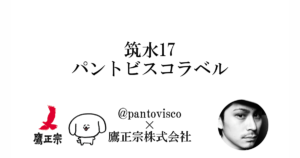


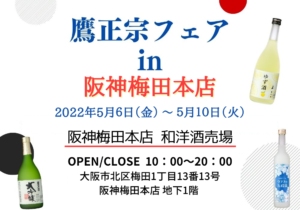
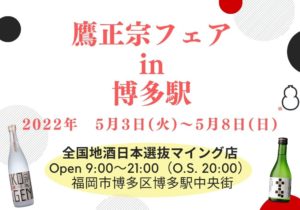






-212x300.jpg)


-212x300.jpg)














